
浜松市の健康経営支援について
〜浜松ウェルネスプロジェクト〜
講師 浜松市副市長 山名 裕 氏
【講演概要】
浜松市は健康長寿日本一、産業力を基盤に発展してきたという強みを活かし、ウエルネスシティ(予防・健幸都市)の実現を目指す浜松ウエルネスプロジェクトを推進している。市民の健康増進、地域企業の健康経営の促進、ヘルスケア産業の創出を3つの柱に、浜松ウエルネス推進協議会と浜松ウエルネス・ラボという2つの官民連携プラットフォームを組織し、様々な事業を創出・展開中。2024年にはウエルネスアンバサダー制度を創設し、市民への情報発信を行っている。
健康経営とは、従業員の健康保持・増進の取組を投資と考え、健康管理を経営的視点から戦略的に実践することである。国には健康経営優良法人の顕彰制度がある。健康経営の効果は、従業員の健康状態改善、ヘルスリテラシーの向上、組織の活性化、企業ブランドイメージの向上、人材の確保・定着等と言われている。市内の健康経営優良法人の認定数は昨年度220者まで増加する一方で、制度を知らない企業も5割存在。啓発活動としてチラシ配布、セミナー等を実施している。また、公共調達や制度融資における優遇措置、保健師による職場での講座開催、浜松市ウエルネスプロジェクトHPの活用、健康経営の取組を行う中小企業等への補助金交付、さらに今年度の新規事業として、健康投資効果分析事業を実施している。昨年は市職員向けに健康経営の取り組み方針を示す「浜松健幸宣言」を策定・公表し、今年3月、浜松市は政令市初、県内自治体初となる「健康経営優良法人2025(大規模法人部門)」に認定された。健康経営は地域の持続的発展のために不可欠である。

「健康経営」取り組み事例
〜社員に寄り添う健康づくり〜
講師 株式会社アトランス 代表取締役 渡邉次彦 氏
【講演概要】
当社は浜松市中里町に本社を持つ運送会社である。取組のきっかけは社員の高齢化、トラック業界だけが健康起因事故が増えているという課題だった。健康経営の必要性を感じていたが、コストや手間をかけられない。協会けんぽ静岡支部様から、「ふじのくに健康宣言」をして健康経営優良法人の認定を目指してはどうかとご提案を受け、取組を始めた。総務の社員2名を健康づくり担当者に任命。具体的には、再検査対象者へのイエローカード、ピンクカードによる受診勧奨、浜松市出張講座、ブレス浜松様による健康体操実演、常葉大学健康プロデュース学部様による鍼灸講座などを受講、「健康だより」を発行、月1回エコ&安全ミーティングを実施、保健師による保健指導を受けた。社内飲料自販機にトマトジュースなどのラインナップを加え、熱中症予防啓発として期間限定50円で販売、メンタル不調者に対し社外相談窓口を設置した。成果としては、要再検査者が19%減り、健康な社員が増加、ヘルスリテラシーが向上した。若者の採用が増え、平均年齢の上昇を抑制、第三者機関による企業風土調査で社員満足度が改善し、2022年には浜松ウエルネスアワードの浜松ウエルネス大賞(健康経営部門)を受賞した。サントリーウエルネスOnline、浜松市SDGs推進プラットフォームでの情報発信、健康経営を進める上でのポイントは、社員が主役、できるだけコストをかけない、パートナー様としっかり連携をしていくこと。健康経営は社員と会社が共に同じ方向に歩むことのできるツールである。

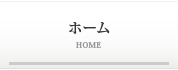
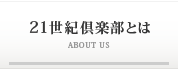
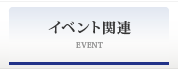
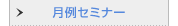
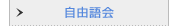


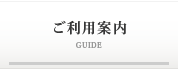












































































































2025年11月26日(水)21世紀倶楽部月例セミナー
『歌声合成技術 VOCALOIDと新しい音楽』
講師 ヤマハ株式会社 研究開発統括部 剣持秀紀 氏
【講演概要】
VOCALOID(ボーカロイド)とはヤマハが開発した、歌詞と音符を入力するだけで歌声を合成することができるソフトウェアおよび技術。人の声から採ったサンプル(素片)をつなぎ合わせて合成する。歌声の素片を集めたものがボイスバンク。ヤマハは他社にこのボイスバンクを開発する権利と歌声合成のためのソフトウェアをライセンスすることからVOCALOIDのビジネスをスタートさせた。その代表格はクリプトン・フューチャー・メディア株式会社(以下クリプトン社)が作った「初音ミク」だ。VOCALOIDの名前の由来はvocal+oid(~のようなもの)。2000年に開発を開始し、2003年に発表。2004年に最初の製品が発売されたが、販売は不振。2007年に声帯の振動と息の成分が混然一体となる人間の声に近づいたVOCALOID2を発表し、クリプトン社が8月31日に「初音ミク」を発売。爆発的ヒットとなった。その後もバージョンアップを重ね、2014年にはVOCALOID4を発表。2022年にはAIの考え方を取り入れたVOCALOID6が発売され現在に至る。
歌声は音声と楽器の両方の性質を持つ。VOCALOID5までの方式では、実際の歌手の歌声の素片を音色操作して滑らかにつなぐために加工をする。また、歌声は音符より前に子音が出るので、音符に母音を揃えるタイミングの調整にも苦労した。VOCALOID:AIはDeep Neural Networkの考え方を使い、実際の人間の歌声で音符と歌詞と歌声の関係を学習させた後、音符と歌詞を入れると、推定した歌声が出る方式。それを人間が修正できるソフトウェアである。
VOCALOIDを開発した理由は、歌声以外は打ち込みによる音楽制作が可能になっていた2000年頃、楽器メーカーとして歌声打ち込みの決定打を開発したいということだった。当初はバックコーラスや仮歌での使用を考えていたが、初音ミクが7年でリードボーカルを可能にした。メジャーデビューし、オリコン1位。昨年の10代のカラオケランキングではトップ10のうち3曲がVOCALOIDで作られた楽曲である。開発・事業化にあたっては「歌声を合成する」という概念をなかなか理解してもらえなかったが、初音ミクの普及によって理解されるようになった。今年の4月にはNHKの「新プロジェクトX」に取り上げられた。
合成された歌声と人間の歌声の違いは、VOCALOIDは人間の体の一部以外のものを使って音楽を作る、つまり楽器であるということ。そして、例えば「初音ミク」といったシンボルが歌っていると錯覚させる新しい楽器なのである。VOCALOIDによってそれまでありえなかった旋律や歌詞、人間に不可能な速さや音域を持つ新しい音楽が生まれた。このように楽器による音楽の変化は、ベートーヴェンの時代やサクソフォンの発明でも見られる。戦前の文芸評論家・平林初之輔は『文学及び芸術の技術的革命』という本の中で「機械が芸術を変える」と述べている。そして、それに対する怖れはあるが、その先に何か新しいものが必ず生まれると言っている。また音楽は社会によっても変化。フランス革命を経て音楽は市民のものになった。今はインターネットの発達で自分が作ったものを即座に世の中に出せるようになり、AIは様々なことを可能にする。作曲という行為自体も変わり、プロンプティングが作曲となるかもしれない。これからも新しい楽器や技術や社会の変化によって、新しい音楽が生まれ続けると思う。