- ホーム
- イベント関連:月例セミナー
イベント関連:月例セミナー
最近のエントリー
アーカイブ
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年7月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年7月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2018年8月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年1月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2015年7月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2014年9月
- 2014年7月
- 2014年5月
- 2014年3月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
静岡新聞社・静岡放送 21世紀倶楽部
〒430-0927 静岡県浜松市中央区旭町11-1 プレスタワー15F TEL(053)455-2001 FAX(053)455-2021
〒430-0927 静岡県浜松市中央区旭町11-1 プレスタワー15F TEL(053)455-2001 FAX(053)455-2021

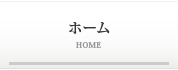
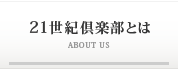
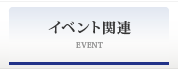
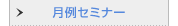
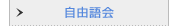


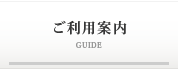
2022年3月25日(金)21 世紀倶楽部 月例セミナー
講師:日本銀行静岡支店長 野見山 浩平 氏
演題:静岡県経済の現状と展望
【講演概要】
わが国の実質GDPはコロナ禍で落ち込む以前の水準に近づいている
が、欧米に比べて戻りが弱いのは社会活動の自粛制限が強く個人消
費活動が弱いことが原因。中高年層の消費活動が積極的になると本
格的に消費が動き出すだろう。
ものづくりではデジタル関連の輸出の伸びが著しい。この先は半導
体などの供給制約と感染症の影響が徐々に和らぐもとで回復していく
見通しであるが、それ以外にも米国の利上げ、ウクライナ情勢の影響
などが回復を脅かす恐れもある。
欧米ではインフレが進み金融引き締めに転換しているが、比べて日本
の物価上昇はまだ低水準。海外発のインフレの悪影響を抑えるために
も現行の金融緩和政策を維持していく。
静岡県経済をみると個人消費ではコロナの影響を受けた巣ごもり消費
が顕著。ものづくりに関しては、半導体などの供給制約が長引いてい
ることから生産や輸出の低空飛行が続いている。こうした中、静岡県
経済が直面する課題を考えてみる。① 【サプライチェーン問題への対
応】突然部品調達ができなくなるリスク回避のため在庫の持ち方を工夫
したり、調達ルートを複数確保したり、部品を自社製造へ切り替えたり
など。②【対面型サービス消費の建て直し】例えば多人数の飲食や団体
旅行などのサービスを個人向けビジネスに転換するなど。③【価格戦略
】コストアップが広がる中、日本企業の「よい品をより安く」というビ
ジネスモデルは見直しの時期を迎えているのではないか。④【膨らんだ
債務返済と事業の見直し】これからゼロゼロ融資の返済期を迎える中で
企業にはリストラの動きがみられる。
また今後、大企業主導でバリューチェーンの「脱炭素」に向けた移行
が進んでいくだろう。しかし中小企業にとって一足飛びに転換するのは
大変難しいため、まずは省エネから始める移行期間(トランジション)
を持つほうが現実的だ。こうした考えは国際的な議論では「脱炭素に背
を向けている」と誤解されることもある。日本は脱炭素の国際的ルール
を作る議論に積極的に参加し、国益を念頭に置いて直接交渉していくこ
とが大切だと思う。そして中小企業は専門家や行政、エネルギー会社等
と連携して答えを探していくことが望まれる。
歴史を振り返れば世界的な経済ショックはこれまでに何度もあった。し
かしバブル崩壊後の日本は、すくんでしまい未来への投資を止めてしま
う傾向が強かったように思う。結果、デジタル化など海外に遅れを取っ
てしまった。今、経済成長のエンジンは決して止まったわけではなく日
本経済には十分なおカネがある。これを有効に活用し経済を回していく
ことが重要であると改めて強調したい。