- ホーム
- イベント関連:月例セミナー
イベント関連:月例セミナー
最近のエントリー
アーカイブ
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年2月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年7月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年7月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2018年8月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年1月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2015年7月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2014年9月
- 2014年7月
- 2014年5月
- 2014年3月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
静岡新聞社・静岡放送 21世紀倶楽部
〒430-0927 静岡県浜松市中央区旭町11-1 プレスタワー15F TEL(053)455-2001 FAX(053)455-2021
〒430-0927 静岡県浜松市中央区旭町11-1 プレスタワー15F TEL(053)455-2001 FAX(053)455-2021

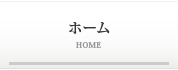
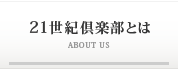
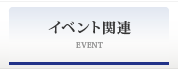
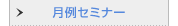
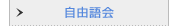


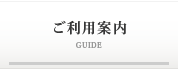
2025年9月24日(水)21世紀倶楽部月例セミナー
『静岡における宇宙・航空産業のポテンシャル』
講師 羽佐間研究所 所長 増田和三 氏
【講演概要】
焼津市出身。アポロの月面着陸を見て宇宙の仕事を志す。名古屋大学工学部前期博士課程修了後、三菱重工入社。1993年社内奨学金を得てマサチューセッツ工科大学に留学。帰国後宇宙ステーション補給機システム設計に携わる。役職者定年を機に静岡に戻り、2015年から今年3月まで静岡理工科大学教授。現在は宇宙開発と地元の子ども向け活動を行う羽佐間研究所を藤枝に開設するほか、JAXAの宇宙戦略基金審査員、名古屋大学非常勤講師などを務める。
三菱重工での最初の仕事は無人有翼往還機(HOPE)の再突入飛行制御だったが、これは開発取りやめに。次の再突入実験機(OREX)は飛行成功。そして宇宙ステーション補給機(HTV)には20年間携わった。国際宇宙ステーション(ISS)は2009年から実運用が開始され、日本人宇宙飛行士が長期滞在。その間に9機のHTVが物資を運んだ。HTVは6トンの物資補給能力を持つ大型補給機で、船内外への大型物資を補給可能。最大の貢献は自律的な軌道上の輸送手段を確立したこと。最後の仕事として有人輸送機や月・惑星への探査機などにつながる次世代の軌道上輸送機を提案。10月21日にそのHTV-Xの初号機が打ち上げ予定だ。
静岡に戻ってからは、無人航空機開発を県に提案。無人航空機にはマルチロータ(ドローン)、40年以上の実績のあるヤマハの無人ヘリコプターなどがあるが、提案した垂直離着陸機は時速100キロ以上で将来的には100キロくらいの荷物が運べるもの。静岡県は、大正時代に日本初の旅客機が浜松で開発され、昭和初期には東京~下田~清水の定期航空路があった。現在は空港・飛行場が3カ所あり、フジドリームエアラインズ、ヤマハの無人ヘリコプターなど航空機産業と関わりの深い場所。関連の業種や人材も多く、製品の開発製造能力があり、ポテンシャルは高い。無人航空機の最大のメリットは「飛び越える」ということで、袋井から下田まで40分。災害時にもダイレクトに行ける。静岡理工科大学に拠点を置き、2016~18年、県の「次世代無人航空機開発・実証業務」事業としてプロト機を開発し飛行試験を実施し、新たなビジネスモデルを構築。社会実装事例として清水港でのマルチロータによる危機管理システム、無人航空機によるコンビニ物流などを提案。2024年3月には県事業でヤマハの無人ヘリコプターを使用した三保・土肥間の駿河湾横断飛行試験が行われた。今年6月には県主導で無人航空機や空飛ぶクルマなどの産業集積に向けたネットワーク組織「次世代エアモビリティ開発推進コンソーシアム」が立ち上がり、県内の試験飛行場を使って実用化をめざしている。
大学退官後は悠々自適に過ごそうと思っていたが、2年前に「静岡で宇宙開発をやりませんか?」と声がかかった。宇宙開発は実は地上への波及がなければ儲からない。大学にいる頃から紙飛行機のような小型軽量の有翼型再突入機を研究・試作していたが、そこで、この開発を推進中。燃料には過酸化水素エネルギーを考えていて、これを地上に反映したら太陽と水で完結する究極の「ポツンと一軒家」ができる技術だ。今は、月の開発にも興味がある。だから「明日、月に行かない?」と言われたらすぐに行けるように、英語と体力を常に整えている。